相続財産と遺産分割協議
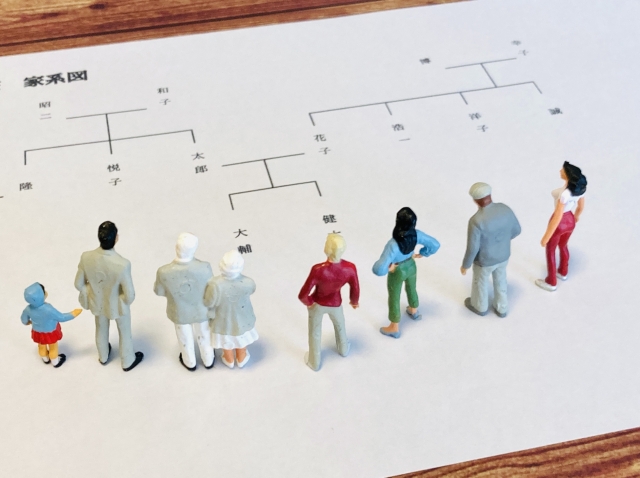
相続財産の確定
相続では被相続人の財産を確定することが最初にする作業です。推定相続人は、被相続人の手元にある金融資産、被相続人所有の自動車などの値段が付く動産、被相続人名義の不動産、及び被相続人の負債に①被相続人がこれまでに推定相続人に贈与した財産及び②推定相続人の働きによって増加した被相続人の財産の価額を合算して相続財産の価額を決定します。
遺産を公平に分けるために考慮すること
生前贈与が既に行われている場合又は遺贈が行われる場合に法定相続分又は指定相続分どおりに被相続人の現有財産を遺産分割すると共同相続人間で不公平が生じる可能性があります。そのため、特別受益と寄与分に当たる金額を考慮して各相続人に分配する遺産の価額を決定する必要があります。特別受益は上の①に、寄与分は上の②に相当します。
特別受益
遺贈された財産、及び婚姻や養子縁組若しくは生計の資本として生前贈与された財産が特別受益に当たります。特別受益を受けた者が相続人の中にいる場合、特別受益の財産の価額を相続開始時の相続財産の価額に加えて各相続人に分配する遺産の価額を算定します(特別受益の持ち戻し)。ただし、遺贈財産は相続開始の時点では相続財産の中に含まれているので遺贈財産の価額を加える必要はありません。
しかしながら、被相続人が上記のような修正を望まないこと(特別受益の持ち戻しを免除すること)を贈与契約書や遺言で意思表示した場合にはこのような修正を行いません。また、婚姻期間が20年以上になる配偶者に対して居住用不動産を遺贈又は贈与したときは、被相続人が特別受益の持ち戻しの免除を意思表示したものと推定し、遺産分割のための相続財産の中からこの不動産分を除きます。
特別受益を考慮した相続分の具体的な修正方法としては次の方法が挙げられます。相続開始時の相続財産全体の価額に特別受益の価額を加算し、その総額から各相続人に分配する仮の価額を算定します。特別受益を有する相続人についてはその仮の価額から特別受益の価額を差し引いた残額が相続財産の中からその相続人に分配されます。
寄与分
共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に貢献をした相続人がいた場合、その相続人の貢献が被相続人の相続財産の中に含まれている(寄与分)と考え、このことを考慮して相続分を修正します。この貢献には次の行動が挙げられます。
- 被相続人の事業に関する労務の提供、
- 被相続人の事業に関する財産上の給付、
- 被相続人の療養看護、
- その他(例:被相続人の事業に関係のない被相続人への財産上の給付)
寄与分を考慮した相続分の具体的な修正方法としては次の方法が挙げられます。相続開始時の相続財産全体の価額から寄与分を差し引き、その残額から各相続人に分配する仮の価額を算定します。寄与分を有する相続人についてはその仮の価額に寄与分の価額を加えた総額が相続財産の中からその相続人に分配されます。
特別の寄与
例えば、相続人の配偶者は、被相続人を療養看護して被相続人の財産の維持又は増加に貢献しても、遺産分割手続きにおいて財産の分配を請求することはできませんでした。被相続人の親族によるこの様な貢献を特別の寄与、その特別の寄与をした親族を特別寄与者と呼び、民法改正により特別寄与者は、相続開始後、相続人に対してその寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました。
この特別寄与料を請求するには、被相続人に対する特別寄与者の寄与が無償であったことが条件として存在します。相続があったことを知ってから6か月を経過した後、又は相続の開始から1年が経過した後は特別寄与料の請求はできません。
(例)
- 相続発生時の被相続人の財産額:3000万円
- 子Aが被相続人の介護に要した金額:600万円
- 子Bが結婚時に結婚支度金として被相続人から得た金額:300万円
上記のような例を考えてみます。亡くなった被相続人の相続発生時の財産は3000万円でした。子Aが被相続人の介護のために支払ったお金は、寄与分に相当します。子Bが婚資として被相続人から得たお金は、特別受益に相当します。寄与分と特別受益を考慮した被相続人のみなし相続財産は以下の計算から算出されます。
3000万円-600万円+300万円=2700万円
この2700万円に相続分の割合を掛け算し、それぞれの寄与分と特別受益の額で補正して各々の具体的な相続分を決定します。この例では法定相続分の割合を使用します。
配偶者:2700万円×1/2=1350万円
子A: 2700万円×1/4+600万円(寄与分)=1275万円
子B: 2700万円×1/4-300万円(特別受益)=375万円
特別受益と寄与分を考慮していなかったら配偶者の相続分は1500万円、二人の子の相続分はそれぞれ750万円でした。ここで大事なことは、このルールは、遺留分の算出において考慮する贈与の期間(特別受益では相続発生前10年以内)や相続税額の算出において考慮する贈与の期間(相続発生前3~7年以内)とは無関係であるということです。被相続人が亡くなるまでに被相続人から受けた又は被相続人に施した全ての特別受益と寄与が対象になります。
特別受益及び寄与分についてのまとめ
- 被相続人は遺言で各相続人の相続分を指定できる
- 被相続人が各相続人に生前贈与した財産が特別受益に当たり、各相続人の相続分の指定に当たっては各特別受益を考慮する
- 被相続人の生前にその財産の維持増大に寄与した相続人に対して、その貢献に応じてその者の相続分を修正する
- 被相続人の生前にその財産の維持増大に寄与した相続人ではない被相続人の親族は、その貢献に応じた金銭を特別の寄与料として請求する権利を有する
相続の承認と相続放棄
被相続人の財産に属した一切の権利義務は、相続開始の時から当然に相続人に承継されるものとされています。しかしながら、その中にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含まれている場合があります。そのため、民法は、相続人に対して、①被相続人の権利義務を全面的に承継するか(単純承認)、②相続財産の限度で債務を負担するか(限定承認)、又は③相続人にならないとするか(相続放棄)を選択することを認めています。
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月の熟慮期間の内に単純承認、限定承認、又は相続放棄をすることを選択します。この期間中に被相続人の財産を調査することになりますが、調査に時間がかかるような場合には相続人などの利害関係人の請求により家庭裁判所がこの期間を伸長することができます。
単純承認
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も承継することをいいます。①相続財産を一部でも処分したとき、②熟慮期間が経過したとき、又は③家庭裁判所への限定承認・相続放棄の申述の後に相続財産を隠していたことや債権者に対して背信的行為をしていたことがわかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
限定承認
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務と遺贈を弁済すべきことを留保して承継を承認することをいいます。相続人が複数あるときは、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に対して限定承認の申述を行う必要があります。ただし、複数ある相続人の内の一人でも相続財産の一部を処分したときは全員で限定承認の申述を行うことができなくなり、単純承認することになります。複数ある相続人の中で一番遅く相続の開始があったことを知った者を基準とした熟慮期間が限定承認のための熟慮期間になります。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の死亡により生じた相続の効果を消滅させる行為をいいます。これにより、相続放棄した相続人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。そのため、マイナスの財産だけ相続放棄するというようなことはできません。以前の記事で説明したように、相続放棄した者の子や孫は代襲相続することができません。
相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に申述することで行います。相続放棄すると他の相続人に負担を押し付けることになる可能性もありますので相続放棄を選択するときには事前に他の相続人と話し合ったほうがよいでしょう。また、相続人の全員が相続放棄した場合、それによってすぐに相続財産中の土地や家屋の管理責任が無くなるわけではないことに注意が必要です(民法第940条)。
相続の承認と相続放棄についてさらに詳しく知りたい方は、リンク先の記事をご覧ください。
遺産分割の方法と注意点
相続は被相続人の死亡によって開始し、相続人が複数存在する場合にはその共同相続人が暫定的に相続財産を共有する形をとります。その後、相続財産は、被相続人の遺言に則って又は相続人間の遺産分割協議を経て相続人それぞれに分配されることになります。
各相続人は、この遺産分割までは、相続財産を管理する相続人代表に対し、金銭等の可分の財産であっても当人へのその支払いを求めることはできません。ただし、各相続人は、当面の必要生計費又は葬式の費用に充てるため、相続開始時の相続財産のうちの預貯金の額の3分の1に当該相続人に当てはまる法定相続分の割合を乗算した額の支払いを、150万円までを限度として求めることができます。
遺産分割協議による遺産分割の指定
共同相続人は、いつでも共同相続人の協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができます。
遺産分割協議は、書面を作成し、各相続人が押印をして遺産分割協議書とすることで行います。遺産分割協議書は、被相続人所有の不動産や預貯金の名義変更の手続きにも必要になります。
遺産分割協議に期限はありませんが、民法改正により相続開始から10年を経過した後にする遺産分割協議では特別受益及び寄与分を考慮せずに遺産分割をすることができます。
共同相続人間で協議が調わないとき、又は協議ができないとき、各共同相続人は、遺産の全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所は、まず調停により分割を試み、調停による分割が調わないときは審判による分割を行います。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、居住している住宅の所有権を有しない被相続人の配偶者が、被相続人の死後もその住宅に住み続けるようにするために定められた権利です。その特徴を以下に挙げます。
- 被相続人の配偶者は、相続の結果として住宅の所有権の全部を相続していなくても相続発生時に被相続人と居住していた住宅に住むことができる
- 遺産分割協議によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は遺言により遺贈の目的とされたときに配偶者は配偶者居住権を取得する
- 配偶者と被相続人との婚姻期間が20年以上であるとき、配偶者居住権の遺贈についても特別受益の持ち戻しがあったものとする
- 被相続人が第三者と共有していた住宅については配偶者居住権を設定できない
配偶者は、遺贈、死因贈与契約、又は遺産分割協議により配偶者居住権を取得できます。配偶者居住権の対象となった住居の所有者は、被相続人の配偶者に配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負います。配偶者居住権の存続期間は、原則としては配偶者の終身の間ですが、遺産分割協議又は遺言によって別途定めることができます。
遺産分割及び配偶者居住権についてもっと詳しく知りたい方は、リンク先の記事をご覧ください。
遺産分割協議についてのまとめ
- 各相続人に配分する遺産の分割は、法定相続分を目安とし、特別受益及び寄与分を考慮して決定する
- 各相続人は、遺産分割までは相続財産の一部の当人への支払いを要求することができない
- 遺産分割協議に期限はない
- 相続開始から10年を経過した後にする遺産分割協議では特別受益及び寄与分を考慮しない
- 相続人の中に行方不明者又は未成年者若しくは制限行為能力者がいる場合にはその者の代理人が遺産分割協議に参加する
行政書士は、相続人のために被相続人の相続人調査及び財産調査をし、それらの調査を基に遺産分割協議書を作成することができます。
より、まずはお気軽にご相談ください